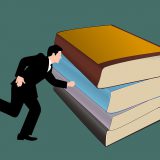今年で8回目の開催となる Kyotographie 京都国際写真祭(www.kyotographie.jp)、従来は毎年春に開催されていましたが、今年は新型コロナウイルスの影響で9月19日から一ヶ月間、京都市内各地で開かれています。
去年は丁度、タイから友人が京都を訪れていたので二人でメトロのオープニングイベントで飲んで騒いだり、ワンデーチケットを購入し自転車で回ったのが懐かしい。早くウイルスが収束し、再び自由に旅が出来るようになってほしいです。
今回は印象に残った写真展をいくつかご紹介します。

今年はワンデーチケットの販売はなく、全メインプログラムに入場できるパスポートを一般4,000円、学生であれば3,000円で購入できます。サテライトイベントも含めるとまわりきれないほどの入場無料会場も提供されています。
新型コロナウイルス感染防止として、各メイン会場で検温と消毒、また事前に名前は連絡先をウェブ登録し、各会場で誰がいつ入場したかをバーコード読み取りで記録するなど、安心安全対策がなされていました。

美術館だけではない会場も Kyotographie の楽しみな要素です。過去の展示では廃墟となった元製氷所や、京都新聞の印刷工場跡など、普段訪れることのないスペースに足を踏み入れることができました。

写真は主にウォン・カーウァイ全盛期「ブエノスアイレス」や「花様年華」の時期に撮影された作品でした。

この数年はホテルやマンションの建設ラッシュの為、数々の立派で京都らしく美しい町家が解体されていくのを心寂しい気持ちで見てきました。解説がなかったので今回の作品に関するアーティストの真の意図はわかりませんが、この作品は失われていく京都での日常生活を表現しているようで、私にとっては、もうすぐ無くなる町家や木造建築独特の香りなど、消えていく風景や暮らしの文化を感じる貴重な機会でした。

The Terminal に展示された写真は全て京都に暮らしていると「ここ知ってる!」「見覚えあるけど、うーんどこやろ」と思える作品ばかりです。京都大学関係では吉田寮の写真が2枚ありました。なじみの商店街や路地奥の飲み屋など、ここでも建設ラッシュ前の京都の生活が伺えます。

上記の写真の前にたどり着く前には身体の不自由や貧困などリアルで厳しい高齢者の日常が伺える小さなスナップ写真が並び、強烈な孤独感、虚しさが漂っていました。途中で退出していく方もいらっしゃったほどです。そして、重い足のりで階段を上がった二階の大部屋にはたった一枚の大きな笑顔。生きることに対する喜びと気力を感じました。