以前のブログで、持続可能な観光が求められる背景について紹介しました。後編の今回は「日本版持続可能な観光ガイドライン(Japan Sustainable Tourism Standard for Destinations:JSTS-D)」をご紹介します。
72% サステナブルな旅行を支持
オンライン旅行予約サイトを運営するBooking.comの調査では、世界の72%が「サステナブルな旅行を希望」するというデータがあります。
旅行者のおよそ4分の3(72%)が「次世代のために地球を守るには、人々は今すぐ行動しサステイナブルな選択を行う必要がある」と回答.
Booking.com Sustainable Travel Report 2019
SDGsと同様に、観光においても持続可能性(サステナビリティ)を意識する旅行者が増えているということですね。近い将来、旅行者から選ばれる観光地になるための一つの要素になる可能性がありそうです。
JSTS-Dとは
2020年6月観光庁は日本版持続可能な観光ガイドライン(JSTS-D)を公表しました。JSTS-Dは、客観的なデータ計測と中長期的な計画をもとに総合的な観光地マネジメントを行う指標です。
参考:「日本版持続可能な観光ガイドライン」(観光庁)https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001350848.pdf
持続可能な観光を指標を用いて科学的に取り組む動きは、2000年代初頭から国連世界観光機関(UNWTO)を中心に進められてきました。JSTS-Dは、国際基準であるGSTC-D(Global Sustainable Tourism Criteria for Destinations:観光地向けの持続可能な観光の国際基準)に準拠する指標として開発されました。世界で導入されているいくつかの指標は、一部日本の現状に合わない部分もありました。そこでJSTS-Dは、日本に必要のない項目は省き、一方で日本の現状で取り組むべき観光財源、感染症対策、民泊対策などの項目が新たに追加されました。日本の各地域に導入しやすく改良されていると言えます。
JSTS-D 3つの役割
観光地をマネジメントするためのツールであるJSTS-Dには、3つの役割があります。
- 自己分析ツール
- コミュニケーションツール
- プロモーションツール
JSTS-Dに取り組むと、地域の強みや課題を客観的・定量的に把握することができ(=自己分析ツール)、その結果を地域のステークホルダーと共有することで地域づくりや観光の取り組みについて合意形成が行いやすくなること(=コニュニケーションツール)が期待されています。そして前述のブッキングドットコムの調査結果からもわかる通り、持続可能な観光への取り組みを表明することが旅行者に評価されることになります。(=プロモーションツール)
中長期の視野で考える持続可能な観光
持続可能な観光という概念は、誰もが賛同するように思います。では観光地でJSTS-Dのような指標を用いた観光地マネジメントの導入は進むでしょうか。私がお話しする機会のあったDMO職員や行政職員の方(計7人)の中には、積極的に導入を検討すると回答した方はいませんでした。どの方も考え方に理解を示すものの、持続可能な観光のための手段として活用するかは様子見という印象です。観光地ごとの特性もあると思いますし、訪日外国人旅行者が激減している今は優先順位が下がるかもしれません。しかし今後訪日外国人旅行者がどのような回復を見せるかはまだわかりませんが、回復する時に備えて中長期の視野で持続可能な観光を考えることも必要でしょう。
理解を深める
私が在籍している観光MBAコースでは、観光地経営について学ぶ「デスティネーション・マネジメント論」という科目が提供されています。今回の「持続可能な観光」は観光地マネジメントの一分野です。2019年度の授業では、アジアエコツーリズムネットワーク理事長やNPO法人日本エコツーリズム協会理事を歴任する株式会社スピリット・オブ・ジャパン・トラベル代表取締役高山傑氏から、サステナブル・ツーリズムについて学びました。
私自身もう少し理解を深めるために、近々持続可能な観光を推進する国際的な機関であるグローバル・サステナブル・ツーリズム協議が主催する3日間のトレーニングプログラムに参加する予定です。持続可能な観光に対する理解を深めてまたこちらのブログで紹介しますね。


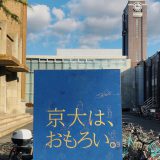
[…] 来週の後編では、これから各地域への導入が期待されるJSTS-Dの内容をご紹介したいと思います。(後編はこちら) […]