アイキャッチ画像はびわ湖テラスで撮った写真です。
京都は琵琶湖と密接な関係があります。
京都という街が平安京として都に選ばれた経緯の一つとして、三方を山に、一方を池に囲まれているという”四神相応”が満たされているからというものがあります。
参考 四神相応ja.wikipedia.org三方の山はなんとなくわかりますね。北は丹波高地。東は大文字山。西は嵐山。
でも、南は…?南山なんて聞いたことないですよね。
今や京都から南に進んでいくと、学研都市付近の丘陵地帯にぶつかるまでは平野が広がっていて、なにもぶつかる山も池もありません。今や京都が四神相応を満たしているかというと、そうでもないわけです。
でも、昔は四神相応を確かに満たしていました。京都の南側に、巨椋池という池があったんですね。
以下が1945年の終戦直前の地図です。

伏見の南、宇治の西側にあるのが巨椋池です。
いまや巨椋池は干拓(埋め立てとは違うが、干上がらせた)されて田んぼが広がり高速道路が通る場所になっています。

この巨椋池の水源は宇治川です。宇治川は上流に遡ると瀬田川に名前を変え、行き着く先は琵琶湖です。
宇治川と瀬田川の流れている場所を地図で見てもらうとよくわかるのですが、大津市街地と山科市街地を流れているわけではありません。信楽に近い山の中を流れているといったほうが正確なくらいです。
昔は、琵琶湖の水は京都の人々の生活用水として京都と関わっていたわけではない、ということです。
どのような京都と琵琶湖の関係があったかというと、巨椋池を形成し、四神相応を満たす土地を形成するという形で京都と琵琶湖が関わっていたんですね。
京都の人々が琵琶湖の水を生活用水として使うようになるのは、1890年に琵琶湖疏水が完成したときからです。
琵琶湖疏水は現役で稼働しています。生活用水としての役割が大きいのは言うまでもないのですが、観光資源としても非常に価値があります。
特に桜の季節は圧巻です。

また琵琶湖は、純粋な水の利用だけでなく、交通にも大きな関わりを持っていました。
明治時代に、日本で鉄道が開通しはじめた時期です。資源不足などが理由で、東海道線を一気に全線開通させるなんて到底無理ですので、部分ごとに東海道線が開通していったのですが、滋賀県は敷設を後回しにされました。
なんでかというと、大津~長浜間を琵琶湖の船で移動することができたからです。
自動車なんてない時代ですから、船で移動できるってのは当時ではもともと結構恵まれてます。
なので、船で移動することができない陸地のほうに鉄道を敷設することを優先させたんですね。

京都と琵琶湖の関係は、明治時代から、昭和に巨椋池が干拓されるまでの間がピークだった、と言えるかもしれないですね。
とにかく、琵琶湖は京都とかなり関わりの深い自然環境です。京都の魅力を語る上で、琵琶湖は外せない、と言えるのではないでしょうか。

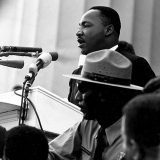

[…] 清水寺すぐそば。祇園からタクシーで行きましたが、少し回り道をしないとたどり着きませんでした。雰囲気は◎体育館が42席を有する天井の高いレストランへ変貌、既存の建物改修部分の34室の他、増築で14室を増やしている。過去記事で「四神相応」について木村氏が書いてくれていますが、このホテル青龍の名前の「青龍」は四神の「青龍」から来ているそうです。つい先日の土曜日、こちらのホテル青龍にあるK36というルーフトップバーに行ってきました。 […]